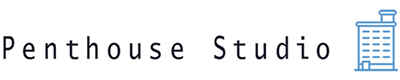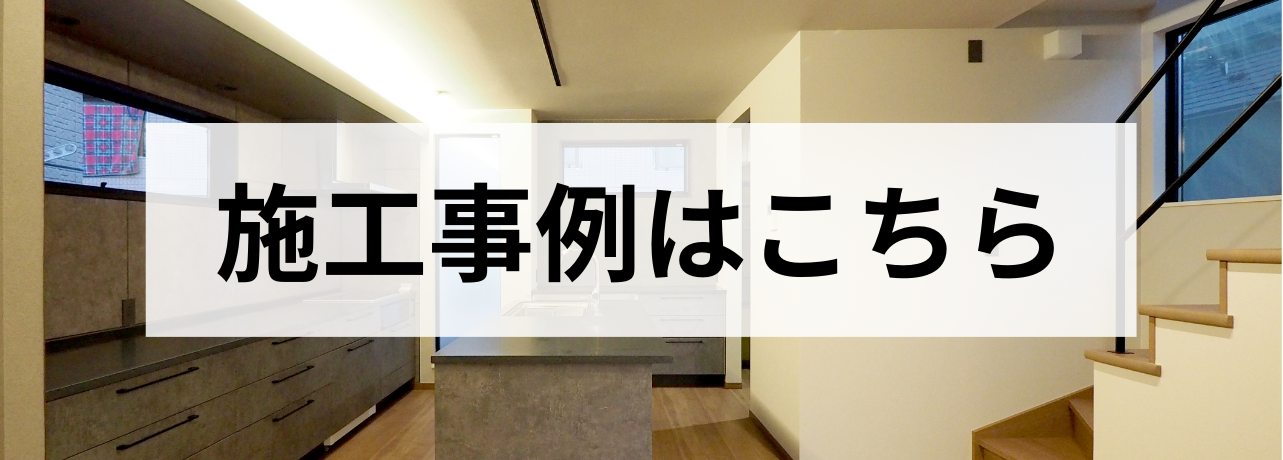床材の種類と特徴を設計事務所が徹底解説!理想の家づくりは足元から2025.07.25
- たくさんの種類の中からどの床材を選べばいい?
- 坪単価はどう計算する?
- 坪単価を抑えるコツは?
家づくりにおいて、間取りやデザインと同じくらい重要なのが「床材」選びです。毎日触れる場所だからこそ、見た目だけでなく、機能性やメンテナンス性、そして家族構成やライフスタイルに合ったものを選びたいものです。
この記事では、そんな疑問や要望をお持ちの皆さまに向けて、設計事務所の視点から、代表的な床材の種類とその特徴、メリット・デメリット、後悔しないための選び方のポイントまで詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 各床材の種類と特徴、メリット・デメリット
- 部屋ごとに適した床材の種類
- 床材を選ぶ際の注意点
代表的な床材の種類と特徴
まずは、注文住宅でよく使われる代表的な床材の種類と、それぞれの特徴を見ていきましょう。
フローリング
住宅の床材として最もポピュラーなのがフローリングです。大きく分けて「複合(合板)フローリング」と「無垢フローリング」の2種類があり、それぞれに特徴があります。
複合(合板)フローリング
合板や集成材といった基材の表面に、木目などを印刷した化粧シートを貼り合わせたフローリングです。
【特徴】
複合フローリングは合板などを基材としているため品質が安定しており施工がしやすいのが特徴です。表面の化粧材によって様々な色柄やデザインがあります。
傷や汚れに強いタイプや防水性を高めたタイプ、遮音タイプ、アレルギー物質を抑制するタイプなど、高機能な製品も増えています。
無垢材に比べて温度や湿度による変形が少ないため、床暖房に対応しやすい製品が多いのも魅力です。
【メリット】
複合フローリングは、温度や湿度の変化による反りや伸縮が少なく品質が安定しています。表面加工により傷や汚れに強く、日々のお手入れが比較的簡単でワックスがけが不要な製品も多くあります。
また、無垢フローリングと比較して材料費・施工費ともに安価で、施工が比較的容易なため工期を短縮できる場合があります。
【デメリット】
複合フローリングは、無垢材と比べて木の質感や温もり、足触りが劣ります。
また、経年劣化により表面の化粧材が剥がれることがありますが、部分的な張り替えが困難というデメリットがあります。
【こんな人におすすめ】
無垢フローリング
天然木を一枚板に加工したフローリングです。「木」本来の質と風合い、温もりを感じられるのが最大の魅力です。
【特徴】
使用される木材の種類によって、木目と色味、硬さ、香りが異なります。大きく分けて、柔らかく温かみのある「針葉樹系」と、硬く傷つきにくい「広葉樹系」の二種類があります。
針葉樹フローリング(杉、ヒノキなど)
足触りが柔らかく温かみがあります。比較的安価なものが多いですが、傷つきやすいのが難点です。
広葉樹フローリング(オーク、チークなど)
硬くて傷がつきにくく、耐久性が高いことが特徴です。針葉樹に比べて高価な傾向があります。
【メリット】
天然木を使用した無垢フローリングは、美しい木目や色合い、心地よい香り、温かみのある足触りが楽しめます。年月とともに色艶が深まる経年変化も魅力です。
断熱性と保温性にも優れており、冬は暖かく夏はさらりとした感触が特徴です。天然素材ならではの調湿効果があり、アレルギーの心配が少ないため小さなお子様がいらっしゃるご家庭にもおすすめできます。
【デメリット】
無垢フローリングは天然素材のため、温度や湿度変化で伸縮や反り、割れ、隙間が生じやすく、高温多湿な梅雨時や乾燥しやすい冬場はトラブルが発生しやすくなります。
複合フローリングより柔らかく傷つきやすく、水分を吸収しやすいためシミになりやすいこともデメリットです。そのため、こまめな掃除やオイル塗布などの定期的なメンテナンスが必要で、樹種によってはメンテナンス費用が高価になる傾向があります。
【こんな人におすすめ】
突き板・挽き板フローリング
突き板・挽き板フローリングは複合フローリングの一種で、複合フローリングの安定性と、無垢材の質感を両立したい方におすすめです。
表面に比較的厚めの天然木化粧板を使用しているため、無垢材に近い質感を楽しめます。
基材が合板であるため、無垢フローリングの弱点である反りや割れが起こりにくく、無垢材よりも比較的リーズナブルな価格帯のものが多くあります。
遮音フローリング
遮音フローリングは、主に集合住宅で階下への生活音を軽減するために、フローリング材の裏側に特殊なクッション材が貼り付けられたものです。
戸建て住宅でも、2階の足音や物音が気になる場合に、1階天井の防音対策と合わせて採用されることがあります。クッション材により踏み心地がややフワフワとし、歩行時に摩擦音が発生することもあります。
クッションフロア
塩化ビニール(PVC)素材でできたシート状の床材です。CFシートとも呼ばれます。
【特徴】
クッションフロアは耐水性に優れていることが最大の特徴です。木目調、石目調、タイル調などデザインや色のバリエーションが豊富で、他の床材に比べて価格が安価です。
【メリット】
クッション性があり足腰への負担が少なく歩行感がソフトで、転倒時の衝撃もある程度吸収します。
また、素材自体に遮音性があるため、階下への音を軽減する効果もあります。
メンテナンスが楽で維持コストがあまり掛からないうえに、張り替えリフォームも比較でき安価に可能です。
【デメリット】
クッションフロアはフローリングやタイルに比べると耐久性がやや劣り、重い家具を長期間置くと跡が残りやすくなります。
また、ビニール素材は熱に弱いため、高温のものを直接置くと変形や変色を起こす可能性があります。
素材の特性上、質感がチープに見えやすく安価な印象を与えてしまうこともデメリットです。
【こんな人におすすめ】
フロアタイル
塩化ビニールやセラミックなどの素材でつくられた、正方形や長方形のタイル形状の床材です。
【特徴】
フロアタイルには、塩化ビニール製とセラミック製のものがあります。
塩化ビニール製のものは、石材や木材のようなリアルな質感と豊富なデザインが特徴で、Pタイルとも呼ばれます。
セラミック製のものは、焼き物ならではの硬質感と高級感が特徴です。
フロアタイルの一種である、コルクタイルも床材の選択肢として考えられます。コルクタイルは、クッション性と断熱性、防音性に優れる素材で、幼稚園や保育園などで多く採用されています。
【メリット】
フロアタイルは傷や摩耗に強く耐久性が高いのが特徴で、土足で使用できるタイプもあります。耐水性、耐汚染性に優れているため、キッチンや洗面所などの水回りや玄関などに適しています。
また、クッションフロアに比べてデザイン性が高く高級感を演出しやすく、空間にアクセントを与えることができるでしょう。
【デメリット】
フロアタイルは硬いためクッション性がほとんどなく、足音が響きやすい傾向があります。
また、塩化ビニール製のものは熱に弱く、セラミック製のものは衝撃で割れやすいというデメリットがあります。
【こんな人におすすめ】
カーペット
カーペットは柔らかい繊維で作られた床材で、既製品を床の上に敷いて使用する場合と、部屋に併せてオーダーで敷き詰める場合の二種類の選択肢があります。
【特徴】
カーペットは温かみのある雰囲気とソフトな足触りが特徴です。パイル(毛足)の形状、長さ、素材(ウール、ナイロン、アクリルなど)によって様々な種類があります。
【メリット】
カーペットはクッション性が高く転倒時の衝撃も吸収するため、小さなお子様や高齢者のいる部屋に適しています。
また、音を吸収して足音や物音を軽減する効果があり、二階の部屋や寝室にもおすすめです。繊維の間に空気を含むため断熱性が高く冬場の底冷えを防ぐとともに、ホコリが舞い上がるのを抑える効果があります。
【デメリット】
カーペットは水分を吸収しやすく、飲み物や化粧品などをこぼすとシミになりやすいというデメリットがあります。汚れが繊維の奥に入り込みやすいので、こまめな掃除機がけや定期的なクリーニングも必要です。
また、湿気がこもりやすくダニが繁殖しやすい環境になる可能性もあるため、アレルギーが気になる方は注意が必要です。
【こんな人におすすめ】
畳
い草を編んで作られた、日本の伝統的な床材です。近年では、天然のい草の代わりに和紙やポリプロピレンなどを使った、耐久性やデザイン性の高い畳も登場しています。
【特徴】
畳は適度な弾力性が特徴で、直接床に座ったり寝転んだりしたい方には最適です。材質の選定や縁(へり)のデザインなどで和風に寄り過ぎないデザインも可能です。
【メリット】
畳は適度な弾力性で座り心地や寝心地が良く、心理的なリラックス効果もあります。
また、内部に空気を含むため断熱性・保温性に優れており、音を吸収する効果や調湿効果も期待できます。
【デメリット】
畳は日光による日焼けで変色しやすく、湿気を吸収しやすいためカビが発生する可能性があるため適度な換気が必要です。水や汚れにも弱くシミになりやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。
【こんな人におすすめ】
タイル
粘土などの原料を高温で焼き固めた素材です。非常に高い硬度と耐久性があり、住宅では玄関や水回りにおいて使用されています。
【特徴】
タイルは高級感がありスタイリッシュな印象を与える床材です。色や形、サイズが豊富でデザイン性が高く、自分だけのオリジナルな空間を演出できます。
【メリット】
タイルは吸水性が低く耐水性に優れるため、汚れが染み込みにくく拭き掃除で簡単にお手入れができます。傷や摩耗、紫外線による変色にも強く耐久性が高いため、長期間美しい状態を保てるでしょう。
【デメリット】
タイルは非常に硬いため、足音や物音が響きやすく、長時間立ったり座ったりすると疲れやすい床材です。
また、物を落とすとタイルが割れたり欠けたりする可能性があるため、注意が必要です。部分的に破損した場合、同じタイルが入手できないと補修が困難になることがあります。
【こんな人におすすめ】
石材
大理石や御影石などの天然石を、床材用に薄くスライスして加工したものです。
【特徴】
天然石には大理石や御影石といった種類があり、それぞれが独特の質感と風格を持ち合わせるため、空間に深みと高級感をもたらします。
【メリット】
天然石はその耐久性と長寿命が特徴で、適切な手入れをすれば美しさを長く保つことができます。
【デメリット】
天然石の種類によっては汚れや水分が染み込みやすいため、定期的な薬品洗浄や表面剤塗布などのメンテナンスが必要な場合があります。
また、材料費や施工費が非常に高価になる傾向があり、工期も長くなってしまいます。
硬いものを落とすと割れたり欠けたりすることもあり、部分的な補修が難しい場合もあります。
【こんな人におすすめ】
部屋別におすすめの床材
それぞれ特徴を理解した上で、部屋ごとに最適な床材を選ぶようにしましょう。
ここでは、設計事務所の豊富な経験から導き出される、部屋ごとのおすすめの床材をご紹介します。
リビングにおすすめの床材
家族が集まるリビングは、家の中心となる空間です。過ごす時間が長く、来客の目にも触れるため、耐久性と手入れのしやすさ、デザイン性、そしてくつろげる心地よさのバランスが重要になります。
フローリング
最も一般的で、多くの人に選ばれています。温かみがあり、様々なインテリアに合わせやすいのが魅力です。小さなお子様やペットがいる場合は、傷や汚れに強い複合フローリングがおすすめです。質感や経年変化を楽しみたいなら無垢フローリングが良いでしょう。
フロアタイル
デザイン性が高く、モダンでスタイリッシュな空間にしたい場合におすすめです。耐久性も高いですが、硬質なのでラグなどを敷いて足元の冷えや硬さをカバーすると快適性も高められます。
タイル・石材
高級感を演出したい場合に採用します。ただし、冬場は足元が冷え込むため床暖房との組み合わせがおすすめです。
寝室におすすめの床材
一日の疲れを癒す寝室は、リラックス効果と静音性がポイントになります。
無垢フローリング
温かみがあり、落ち着いた雰囲気を演出できます。ラグを部分的に使うのも良いでしょう。
カーペット
足触りが柔らかく、保温性・吸音性に優れているため寝室に最適です。ホコリの舞い上がりを抑える効果も期待できます。
畳
天然の畳は、い草の香りでリラックスできます。布団を敷いて寝るスタイルの方にはぴったりです。
子ども部屋におすすめの床材
子供部屋は、小さい頃は遊び場として、成長すれば寝室兼学習室へとお子様の成長に合わせて用途が変化します。
複合フローリング
広い用途に適したオールマイティな複合フローリングがもっとも無難でしょう。防滑加工や汚れ止め加工を施した機能性フローリングであればなおおすすめです。
クッションフロア
適度にクッション性があり汚れを落としやすいクッションフロアもおすすめです。成長に合わせて気軽に張り替えられるのもメリットと言えます。
玄関におすすめの床材
泥や砂、雨水などで汚れやすい玄関は、耐久性と汚れにくさ、掃除のしやすさが最優先されます。家の顔でもあるため、デザイン性も考慮したいものです。
タイル
耐久性と耐水性、防汚性に優れデザインも豊富です。特に、表面に凹凸のあるタイルは滑りにくく、雨の日でも安全です。デザイン性の高いタイルを選ぶことで、玄関の印象を格上げすることも可能です。
フロアタイル
タイルや天然石材のようなデザインを比較的安価に取り入れられます。耐久性や耐水性も高く、玄関の床材として十分な性能を持っています。デザインも豊富なので、家の雰囲気に合わせて選ぶことができます。
水回りにおすすめの床材
水回りは、水濡れや汚れが頻繁に発生する場所であるため、床材選びには特に注意が必要です。耐水性、防汚性はもちろんのこと、日々の掃除のしやすさも重要なポイントとなります。
クッションフロア
表面がビニール素材でできているため水が染み込む心配が少なく、水回りに最適な床材のひとつです。汚れもサッと拭き取ることができます。最も手軽でコストパフォーマンスに優れている床材です。
フロアタイル
耐水性、耐久性に優れておりデザインも豊富なため、おしゃれな水回りにしたい場合に人気があります。
タイル
耐水性、防汚性が非常に高く水回りには最適な床材と言えます。表面が硬く、汚れが染み込みにくいため、掃除も簡単です。ただし、冬場は表面が冷たく感じることがあるため、床暖房と組み合わせると快適に過ごせるでしょう。
高齢者や小さなお子様がいらっしゃる家におすすめの床材
ご家族に高齢者や小さなお子様がいる場合は、クッション性や滑りにくさなどの安全性を重視すべきでしょう。それに加えて、お手入れのしやすさと防音性なども考慮したいところです。
無垢フローリング
パインなどの針葉樹フローリングは温かみがあり柔らかく、幼児の部屋にもおすすめです。舐めても害の無い蜜蝋ワックスなどの天然オイルでお手入れすれば、お子様が床に寝転がっても安心です。
クッションフロア
クッション性があり転倒時の衝撃を和らげ、汚れてもサッと拭き取れます。比較的安価なので、劣化したら気軽に張り替えられるのもメリットです。
コルクタイル
天然素材であるコルク樫の樹皮を加工して作られており、自然な風合いと温かみが特徴です。クッション性に優れているため、転倒時の衝撃も和らげます。
床材選びのポイント
多くの床材の中から最適なものを選ぶために、押さえておきたいポイントを解説します。
機能性を考慮する
まずは、その部屋に必要な機能と優先順位をご家族で話し合って整理しましょう。
人が多く歩く場所か?傷つきやすい使い方をするか?
水がかかる可能性は高いか?
階下への音は気になるか?静かに過ごしたい部屋か?
滑りにくさや衝撃吸収性は必要か?
掃除のしやすさは?定期的なワックスがけやクリーニングは可能か?
冬場の足元の冷えは気になるか?
これらの優先順位を考え、子どもの成長や将来的な介護などのライフスタイルの変化の可能性も考慮に入れながら検討することが大切です。
カタログだけでなく実物を確認
カタログやインターネット上の写真だけでは、色味や質感、スケール感はなかなかつかめません。気になる床材が見つかったら、必ずサンプルを取り寄せて比較検討しましょう。
可能であれば、ショールームなどで実際に施工されている状態を確認するのがベストです。広い面積で見たときの印象や、光の当たり具合による見え方の違い、そして何より実際に触れてみて、足で踏んでみて、その質感や触り心地を確かめることが非常に重要です。
床暖房の有無
人気の床暖房ですが、床材によっては設置できない、または注意が必要な場合があります。床暖房を設置する場合は、検討している床材が対応しているか必ず設計士やメーカーに確認しましょう。
比較的安心して採用できますが、製品ごとの仕様確認が必要です。
熱による乾燥で変形のリスクがあるため、事前に十分に乾燥された床暖房対応品を選ぶ必要があります。
塩ビ系の素材は熱に弱いものもあるため、床暖房対応品かを確認しましょう。
熱伝導率が高く床暖房との相性が良い床材です。
まとめ
ここまで、様々な床材の種類と特徴、選び方のポイントについて解説してきました。
床材は、内装の中でも空間の印象を左右する重要な要素です。デザイン性だけでなく、日々の暮らしの快適性や安全性、メンテナンスの手間にも直結します。
Penthouse Studio一級建築士事務所では、施主様の理想の家づくりにあたって、設計だけではなく資金計画や土地のご紹介、建設工事とその後のアフターフォローまで、建築エージェントとして全てのプロセスに関わらせていただきます。
また、首都圏の狭小エリアを中心に、戸建注文住宅の設計を400件以上担当した実績もございます。
施主様を決して後悔させないよう、複数の選択肢を示しながら家づくりのプロセスを慎重に歩みます。
施工事例も更新中ですのでぜひご覧ください。