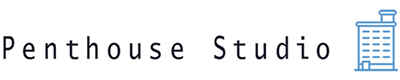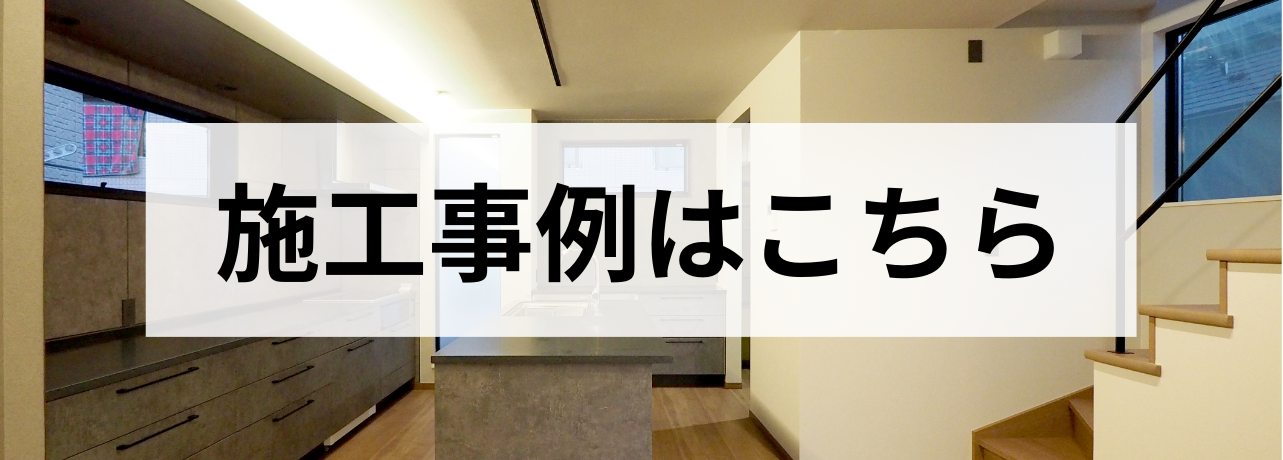注文住宅の坪単価、本当の意味は?賢くコストを抑える方法まで徹底解説!2025.04.15
- 坪単価には何が含まれる?
- 坪単価はどう計算する?
- 坪単価を抑えるコツは?
注文住宅を検討する過程では「坪単価」という言葉を良く耳にすると思います。「坪単価〇〇万円」という数字は、家づくりの予算を考える上でひとつの目安になるでしょう。
しかし、提示された坪単価が安くても、最終的な建築費用が予算をオーバーしてしまったというケースは少なくありません。そもそも坪単価には何が含まれているのかという疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、注文住宅における坪単価の正しい意味や注意点、そして賢くコストを抑えながら理想の家を実現するための具体的な方法について、設計事務所の視点から分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 坪単価の正しい計算方法と本当の意味
- 坪単価に含まれる費用、含まれない費用
- 予算内で理想の家を建てるためのコスト削減のコツ
注文住宅の坪単価とは?
注文住宅を建てる際に頻繁に耳にする坪単価について、その基本的な意味合いを確認していきましょう。
坪単価の定義
坪単価とは、建物の建築にかかる本体工事費を建物の延床面積(各階の床面積の合計)で割って算出される数値のことで、1坪(約3.3平方メートル)あたり、どれくらいの費用がかかるかを示しています。
坪単価 = 建物の本体工事費 ÷ 延床面積(坪)
この坪単価を把握することで、検討している住宅のおおよその建築費用を掴むことができます。例えば、坪単価80万円の住宅会社で延床面積40坪の家を建てる場合、「80万円 × 40坪 = 3,200万円」が本体工事費の目安となります。
逆に、先に予算が決まっている場合は、「予算 ÷ 坪単価」でおおよその建築可能な建物の広さを算出することも可能です。
フラット35利用者調査から見る注文住宅の坪単価相場
では、実際の注文住宅の坪単価はどのくらいなのでしょうか。住宅金融支援機構が毎年公表している「フラット35利用者調査」のデータを見てみましょう。
2023年度の調査によると、土地の購入費用を含まない注文住宅の建設費の全国平均は約3,861.1万円、住宅面積の全国平均は36.1坪(約119.5㎡)でした。
ここから単純計算で坪単価を算出すると、3,861.1万円 ÷ 36.1坪 ≒ 約107万円/坪となります。
ただし、このフラット35のデータから算出される坪単価には注意が必要です。これは、建物本体工事費だけでなく、付帯工事費や諸経費などを含んだ「総費用」を延床面積で割っている可能性が高いため、一般的に住宅会社が提示する「本体工事費の坪単価」とは異なる場合があります。
一般的に、注文住宅の建物本体工事費における坪単価の相場としては、70万円〜100万円程度が一つの目安と言われています。もちろん、これはあくまで目安であり、建物の仕様や構造、依頼する会社(ハウスメーカー、工務店、設計事務所など)によって大きく変動します。
坪単価を考えるときの注意点
坪単価は、家づくりの費用感を掴むための便利な指標ですが、いくつかの注意点があります。
あくまで「目安」であること
坪単価は、建物の形状や仕様、設備のグレード、地盤の強さなど様々な要因で変動します。提示された坪単価は参考程度に考え、総額で判断することが重要です。
地域差があること
都市部は土地代だけでなく、人件費や資材の輸送コスト、現場管理に関わる諸経費なども地方に比べて高くなる傾向があります。それに伴って坪単価も高くなるのが一般的です。
坪単価だけで判断しないこと
坪単価が安くても建物の面積が大きければ総費用は高くなり、逆に坪単価が高くてもコンパクトな家なら総費用を抑えられます。また、坪単価が高くても住宅性能が高い家は、入居後の光熱費やメンテナンス費用を長期的に抑えられる可能性があります。
坪単価は床面積に対する費用ですが、実際の住み心地は床面積だけで決まるわけではありません。例えば、スキップフロアやロフト、吹き抜けなどを効果的に取り入れることで、実際の床面積以上の広がりや豊かさを感じられる空間を創り出すことができます。
こうした自由な発想に基づく間取りや立体的な空間構成は、まさに設計事務所の腕の見せ所と言えるでしょう。坪単価という数字には表れない「空間の質」にも目を向けることが、満足度の高い家づくりに繋がります。
坪単価は何が含まれている?
坪単価の計算に使われる「建物の本体工事費」ですが、具体的にどのような費用が含まれているのでしょうか?一般的に含まれる項目と、注意すべき点を見ていきましょう。
建築本体工事費
これは、建物そのものを建てるために直接かかる費用です。家づくりの大部分を占める費用と言えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仮設工事 | 工事用の足場や仮設トイレ、水道・電気などの設置費用 |
| 基礎工事 | 建物を支える土台となる基礎を作る工事 地盤の状態によっては補強工事が必要になることも |
| 木工事(躯体工事) | 柱や梁、土台、屋根組など、建物の骨組みを作る工事 |
| 屋根工事・板金工事 | 屋根材を葺く工事や、雨樋などの設置工事 |
| 外壁工事 | サイディングやタイル、塗り壁など、外壁を仕上げる工事 |
| 建具工事 | 窓(サッシ)や玄関ドア、内部ドアなどの取り付け工事 |
| 内装工事 | 壁紙(クロス)、床材(フローリングなど)、天井材などの仕上げ工事 |
| その他 | 断熱工事、左官工事、塗装工事など |
付帯設備工事費
建物本体に付随する、生活に不可欠な設備の設置費用です。これも一般的に本体工事費に含まれることが多い項目です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給排水設備工事 | キッチン、浴室、トイレ、洗面所などの水回り設備や、それに伴う給水管・排水管の配管工事 |
| 電気設備工事 | 照明器具用の配線やコンセント、スイッチ、分電盤などの設置工事 |
| ガス設備工事 | ガス管の配管工事(オール電化の場合は不要) |
| 空調・換気設備工事 | 24時間換気システムや、場合によっては基本的な空調設備の設置工事 |
諸経費
建設会社が工事を円滑に進めるために必要な経費です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現場管理費 | 現場監督の人件費や、工事現場の運営に必要な費用(光熱費、保険料など) |
| 一般管理費 | 建設会社の本社経費や営業経費など、会社を運営していく上で必要な費用 |
| 各種申請費 | 建築確認申請など、家を建てるために必要な法的な手続きにかかる費用(申請機関に納める手数料は別途の場合あり) |
設計・監理費
建物の設計や、工事が設計図通りに行われているかを確認(監理)するための費用です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設計料 | 建物のデザイン、間取り、構造、設備などの図面を作成するための費用 |
| 工事監理費 | 設計図通りに工事が進んでいるか、品質は確保されているかなどをチェックするための費用 |
坪単価に含まれないもの
坪単価の算出に含まれる費用の範囲は、実は住宅会社によって異なります。特にハウスメーカーなどでは、標準仕様から外れるものをオプション扱いとし、坪単価計算の基となる本体工事費には含めず、別途費用として計上するケースが多く見られます。
一般的に、以下の費用は坪単価に含まれず、別途必要となることが多い項目です。どこまでが坪単価に含まれるのか、必ず契約前に詳細を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地盤改良工事費・杭工事費 | 事前の地盤調査の結果、地盤が弱いと判断された場合に必要な工事費用 |
| 外構工事費 | 門、塀、フェンス、駐車場、庭、植栽など、建物周りの工事費用 |
| インフラ引き込み工事費 | 敷地内に電気、ガス、水道、通信回線などを引き込むための工事費用 |
| エアコン設置費 | 居室に取り付けるルームエアコン本体と設置工事費 |
| アンテナ設置費 | テレビアンテナの設置費用 |
| 照明器具 | シーリングライトやダウンライトなどの照明器具本体 |
| カーテン・ブラインド | カーテンレール取り付けも含め、別途となることが一般的 |
| 家具・家電製品 | ソファやテーブル、冷蔵庫、洗濯機など |
| 網戸 | 標準仕様に含まれていない場合があります |
| 建築確認申請以外の申請費用 | 地域の条例や地区計画など、土地の状況によって必要となる特別な申請費用 |
| 登記費用、ローン諸費用、税金など | 建物本体の工事とは直接関係ない費用 |
坪単価が上がる要因と下がる要因
同じ面積の家でも、坪単価は様々な要因で変動します。どのような場合に坪単価が上がりやすく、逆にどのような場合に下がりやすいのでしょうか。主な要因を見ていきましょう。
坪単価が上がる要因
平屋住宅
二階建てに比べて、屋根と基礎の面積が大きくなるため、同じ延床面積でも坪単価は割高になる傾向があります。
複雑な間取りやデザイン
凹凸の多い形状の建物は、外周が複雑になるため外壁やコーナー部分の材料・工事手間が増え、コストアップに繋がります。また、部屋数が多いと間仕切り壁が増えて材料費や工事費が増加します。さらに、こだわりのデザインや曲線を用いた複雑な形状は施工の手間が増えるため、坪単価が上がる要因となります。
建築資材の価格変動
輸入建材は国際情勢や為替レートなどの影響も受けます。2022年にコロナ禍の影響で輸入木材価格が高騰した「ウッドショック」のように、主要な建築資材の価格が高騰すると、それに伴い坪単価も上昇します。
人件費の上昇
職人賃金の上昇は建築コストに反映され、坪単価を押し上げる要因となります。近年は建築職人の高齢化が顕著になっており、職人確保のためのコストが建築費高騰要因のひとつになっています。
高品質な設備や仕様
グレードの高いキッチンやお風呂、高機能なトイレなど標準仕様から変更すると費用が上がります。また、無垢材フローリング、珪藻土の壁、高性能な断熱材やサッシなどこだわりの建材や仕様を採用すると坪単価は上がります。さらに、造作家具や特殊な照明計画などもコストアップ要因となります。
狭小地や変形地での建築
資材の搬入や工事車両の駐車が困難な場合、手間や費用が余計にかかり、坪単価が上がることがあります。
坪単価が下がる要因
総二階(または総三階)建ての住宅
1階と2階(または3階まで)の面積がほぼ同じで、形状がシンプルな箱型の家は、屋根や基礎の面積が比較的小さく、外壁の凹凸も少ないため、坪単価を抑えやすくなります。
標準的な間取りと標準仕様の採用
部屋数を抑え間仕切り壁を少なくすることで、材料費や工事費を削減できます。例えばお子様が小さいうちは専用の子供部屋が不要ですので、オープンスペースにしておき、将来的に個室にできるように間取りを工夫しておくことなどが考えられます。
また、住宅会社が設定している標準仕様の建材や設備を多く採用することで、コストを抑えられます。なぜなら、標準品は取引量が多いためメーカーから特別な単価で提供されていることが多いためです。
設備の施主支給
エアコンや照明器具、洗面台などを施主が別途購入して支給する(施主支給)ことで、費用を抑えられる場合があります。ただし、保証の問題や取り付け工事費が別途必要になるかなど、事前に住宅会社とよく相談が必要です。
一部内装の施主DIY
壁塗りや棚の取り付けなど、一部の内装作業を自分たちで行う(DIY)ことで、人件費を削減できます。これも、どこまで可能か、安全性は確保できるかなど、住宅会社との綿密な打ち合わせが必要です。
坪単価を抑えるコツ
坪単価は、建物の形状や仕様、選択する設備など様々な要素が絡み合って決まります。どこにこだわり、どこでコストを調整するのか、優先順位を明確にすることが大切です。
ここでは、坪単価を意識しながら、賢く建築費用を抑えるための具体的なコツをご紹介します。
間取りの工夫
間取りの工夫は、コスト削減に直結する重要なポイントです。
コストを抑えるためには、建物の形状をシンプルな箱型にし、水回りをまとめる、部屋数を最適化する、廊下を減らすといった間取りの工夫が重要です。
また、吹き抜けやスキップフロア、ロフトなど縦方向の空間を有効活用することで、床面積を増やさずに開放感や機能性を高めることができます。これらの空間を活かすアイデアや設計力は、設計事務所が得意とするところです。
建材の選択
使用する建材や住宅の仕様を見直すことも、コストダウンに繋がります。
コストパフォーマンスの良い建材を選び、材料の種類を絞ることでコストを抑えられます。また、全ての箇所にコストをかけるのではなく、こだわりたいポイントを明確にし、メリハリをつけることが重要です。それ以外の部分ではコストを抑える、といったメリハリをつけることが大切です。
設備の見直し
住宅設備はグレードによって価格が大きく異なります。設備コストを下げるには、最新・最高級グレードではなく少し前のモデルやシンプルなモデルを選ぶ、住宅会社が得意とするメーカーの製品を選ぶ、施主支給を検討するなどの方法があります。
ただし、施主支給の場合は事前に住宅会社と取り付け費用や保証についてよく相談することが大切です。
見積入札と発注時交渉
建築を依頼する会社を選ぶプロセスや、契約時の交渉も重要です。複数の建設会社から相見積もりを取ることで価格競争が生まれ、適正な価格を引き出せます。
設計事務所に依頼している場合は、相見積もりや入札の手続きを代行してもらえます。見積もり内容を精査し、建設会社と交渉することでコストダウンも可能です。設計事務所は建築のプロとして施主の立場に立ち、建設会社との価格交渉やコスト管理を適切に行い、品質を落とさずにコストダウンを実現するためのサポートを提供します。
これらのコツを参考に、ご自身の予算やこだわりに合わせて、最適なコストコントロールの方法を見つけてください。
まとめ
今回は、注文住宅を建てる上で重要な指標となる「坪単価」について、その意味や内訳、変動要因、そして賢くコストを抑えるためのコツを詳しく解説しました。
坪単価は便利な指標ですが、その数字だけに囚われず、総費用や住宅性能、そして設計の工夫による空間の質といった多角的な視点を持つことが、賢い家づくりを進める上で非常に重要です。
どこにコストをかけ、どこを抑えるべきか、自分たちだけでは判断が難しいと感じることもあるでしょう。そんな時は、ぜひ家づくりの専門家である設計事務所にご相談ください。
経験豊富でアイデア豊かな設計事務所は、お客様のご要望や予算に寄り添いながら、坪単価という数字だけでは測れない価値、すなわち、コストを抑えながらもデザイン性や機能性、快適性に優れた、あなただけの理想の住まいを形にするための最適なプランをご提案します。建設会社との複雑な交渉やコスト管理もお任せいただけます。
Penthouse Studio一級建築士事務所では、施主様の理想の家づくりにあたって、設計だけではなく資金計画や土地のご紹介、建設工事とその後のアフターフォローまで、建築エージェントとして全てのプロセスに関わらせていただきます。
また、首都圏の狭小エリアを中心に、戸建注文住宅の設計を400件以上担当した実績もございます。
施主様を決して後悔させないよう、複数の選択肢を示しながら家づくりのプロセスを慎重に歩みます。
施工事例も更新中ですのでぜひご覧ください。